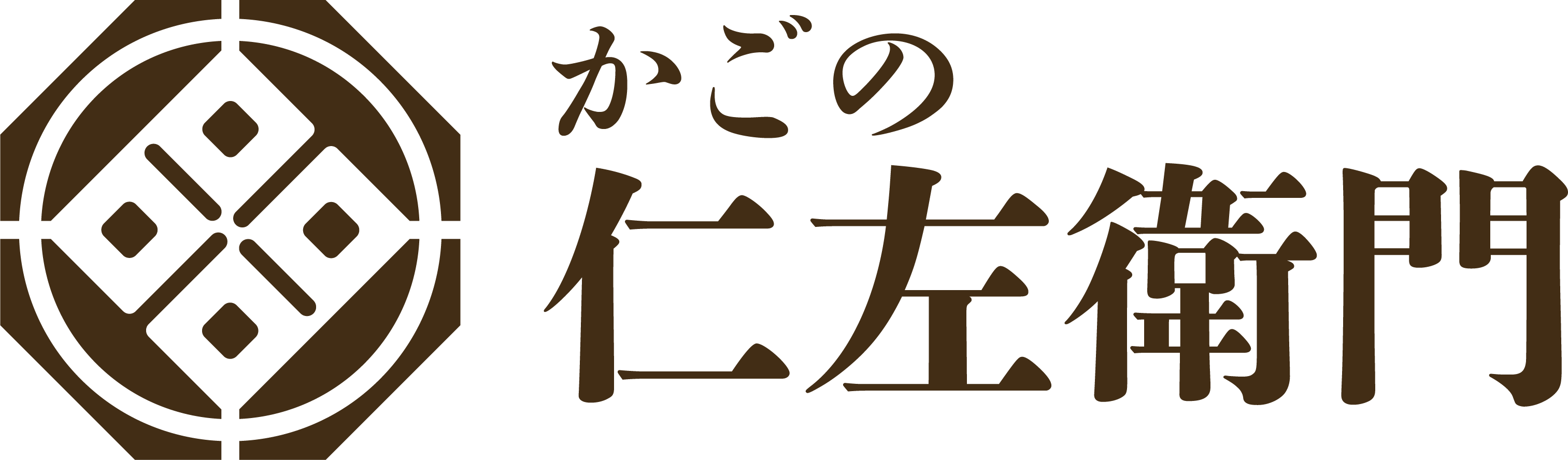アタ製品とは
仁左衛門ショップで販売している小物入れやバッグ、箱などは、18,000余りあるインドネシアの島々の中の、ロンボック島、スンバ島、スンバワ島、フローレス島、バリ島、そしてカリマンタン島にしか自生していないアタ”ATA”を使用しています。(最近はアタがどんどん少なくなり、バリ島ではほとんど採れずカリマンタン島から入れていると聞いています)
現地の職人の話では、「”アタ”という植物は変わり者でね、肥沃な土地で育った物より水も少ないような荒地で育った”アタ”の方がずっと強いんだよ」と言っていました。私は人間と同じだね!と答えた事があります。
山近くに住む”アタ取り”人々は、手弁当で山々に入り、アタを刈り取り、束ねて山の裾野にある小屋に運び、数日そのままに放置。アタについている虫たちが逃げていくのを待ちます。その後、アタの材料は各職人たちの居住区に運ばれ、水をふりかけられ、編むかごの網目の大きさが決められていきます。


職人たちはそれぞれ、大きさの違う幾つか穴が空いている鉄板(直径10cmくらい)を持っていますが、そこにある穴に、ある程度おおざっぱに割いたアタを一本一本通していきます。アタの太さ、つまり網目を均一にする下準備というわけです。また、太い部分、基本的にほぼ同じ太さのアタはかごの骨組みになります。
職人たちは山間部、街中などに住んでいる各自の家々で編んでいます。そして、編み上がったかごを袋に入れて注文をくれた元締めの元に運びます。この時点で職人たちは約束の賃金を受け取ります。


この後、職人たちから受け取ったアタかご3日~1週間天日干しされます。そして天日干しが終わったアタかごは、更に3日~1週間、いい香りのする木々の木っ端やココナッツ椰子の殻で燻製されるのです。
私も昭和の田舎の暮らしの中で、囲炉裏の上の藁束に川魚を刺して燻製にしていたのを覚えています。
燻製にする事で、腐敗を防ぎ保存する事が出来るのです。科学薬品を使わない人間に優しい保存方法です。”いぶりがっこ”や”燻製卵”と同じです。人間の体に害はありません。


バッグの場合、この後持ち手を付け、中布を付けます。ここまでの工程を経たアタかごは、水に強く、使うほど馴染んでやがて燻しの色落ちがなくなり香りも気にならなくなります。そして、時がたつにつれて飴色に変化していきます。

以前、私はアタかごの箱を暗い場所に収納しておいたのですが、ある時思いついて、出し見てびっくりしました。光の当たらない場所に置いた方が激しく変化していたのです。アタかごの良さは時間の経過とともに美しく変化する事です。使い捨てや劣化していく物があふれるこの世界の中で希少なもののひとつだと言えます。